40周年企画 代表×4部門社員 座談会
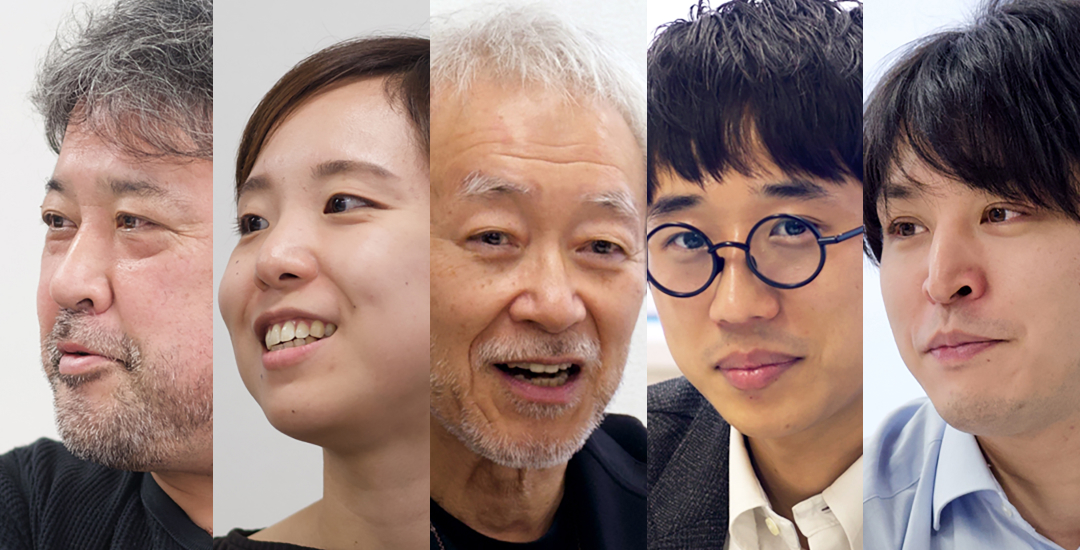
| ※掲載内容は取材当時(2023年11月時点)のものです |
2023年に創立40周年を迎えたシアターワークショップ。長年培ってきた劇場コンサルティングから舞台技術、施設運営、文化イベント事業プロデュースまですべてを強化し、トータル・シアタープロデュース・カンパニーとして本格的に取り組んでいます。新たな目標に向けて代表の伊東正示を中心に、それぞれの部門担当者が想いを語ります。
メンバー
照明チーフ
チーフ
マネージャー
今の時代の、「劇場のあり方」とは
– まず、改めて伺いますがシアターワークショップにとって「劇場」とは何でしょうか。
僕が大学生の頃、小劇場演劇が流行していました。ある意味で劇場を捨てるというような、表現の場として劇場ではないテントや倉庫などを選択した劇団もあって、大学院の修士課程では、そういった非劇場空間がいかに劇的であるかを研究していました。その魅力を追求していくと、重要なのは劇場やホールの大きさや機能ではないわけです。あらゆる要素を省いていったときに残るのは、演者と観客だけであり、一体となってつくりあげる体験の場が「劇場」なのです。熱気や感動が生まれる非日常的な空間、そんな「劇場」をつくりたいとずっと考えてきました。
それぞれの劇場やイベントスペースには個性というか、独特の「顔」がありますよね。空間のサイズや環境が変わるだけで、演じる人たちの表現するものも変わる。そんな演じ手やアーティストのその空間だからこそ生まれる魅力を引き出す、装置みたいな役割なんじゃないかなって思います。

学生時代、公園で上演される3秒くらいの演劇や、商店街の向こうから河童が子どもたちを引き連れて駆けてくるパフォーマンスを観て、とても心が躍ったのを覚えています。誰かが誰かに対して表現しようとする限り、それは演者と観客でつくりあげる「劇場」と言えるのかもしれません。
まさに演劇は、演者と観客のインタラクティブな関係性で成り立つものだと思います。公演の回数を増すごとに作品は日々進化していきますし、いわば、ライブパフォーマンスです。そういう意味でいうと、ストリートピアノを演奏する場だって一種の「コンサートホール」と言っていいですね。
– 確かに音楽やダンス、パフォーマンスに触れられる場は街中のさまざまな場所で増えている印象があります。
劇場やそのようなイベントスペースの役割にも変化があるのでしょうか?

新しい役割を持たせ、コミュニティの中心にしようという動きがありますね。本来のホール機能の部分を小さくして、集会室や練習室といった日常的に開放される空間の割合を増やしたりしています。
一時期、図書館がカフェを設置したりイベントを実施して、居心地の良い「第三の場」(サードプレイス)とうたわれていました。それに倣って、劇場も開かれた広場として、ふらっと気軽に来た人が自由に過ごせる空間にしようというのが文化庁の方針です。
僕は広場ではなく「原っぱ」を目指したいと思っています。広場は「このように使ってください」と整然としたルールがありますよね。一方、原っぱは何をしようが自由です。これは建築論集『原っぱと遊園地』(青木 淳)にもあります。大勢の人たちが集まるのなら、何か新しいものを創造する場にしたほうが断然おもしろいですよ。ルールは自分たちで作ればいい。だって、そもそも演者と観客がいれば、その場所はどこでも劇場になりますから。
そしてそんな原っぱだからこそ、サードプレイスのさらに先の、誰もが気持ちよく交流できる居場所として、「劇場」が第四の場、フォースプレイスになればいいなと思っています。
– 劇場といっても多彩なんですね。
皆さんは劇場やイベントスペースをつくる際、どんなことを意識していますか。
オーナーや地域の方たちの本当に望む劇場やスペースを形にするのはもちろんですが、裏方として、演者が舞台に込めたメッセージを一人でも多くの観客に伝えるサポートをしたいと思っています。そのために環境を整えるのが私たちの仕事なのかな、と。
劇場や場所のことより、アーティストのことだけが記憶に残ってくれるのが理想だと思っています。凝った照明プランでつくり込んでいたとしても、それはアーティストの魅力を最大限に引き出すための照明であって、照明自体のことは意識に残らなくていい。感動するシーンを観たらその体験以外のことはすべて忘れて帰ってくれるのが一番いいと思いますね。
劇場や文化施設を建てた後に、どんな人に来てほしいのか、そこで誰と出会えるのか。すべてをコントロールするわけにはいかないですが、イベントや文化事業のプロデュースを通してそれらをコーディネートするのも、私たちの仕事だと思っています。
シアターワークショップで運営を担当している施設には、劇場だけでなく、平土間の何もないホール空間や、屋外の広場もあります。どんな場所でも、使う人たちのやりたいことが叶えられる場所だろうか?ということを考えるのが大切ですね。搬入やバックヤードの使い勝手なども含めて、使用者の表現しやすさは追求していますね。
日常の中に、「劇場」を
– 劇場や舞台を通して、人生が変わりましたか。
それは今の仕事につながっているのでしょうか。
僕がこの会社をつくった一番のきっかけは、通った小学校のみんなで演劇作品をつくりあげる授業でした。それがきっかけで芝居が好きになり、大学で建築学科へ進んだときに、演劇と建築が交わる場所が劇場なので生涯劇場に携わる仕事をしたいと思ったのです。ただ、いわゆる建築物としての「劇場」だけでなく、僕自身がアートマネジメントの分野も勉強していたこともあって、それが表現者と観客がいればどこでも劇場になるという考えにつながっていますね。

中学生から始めて大学卒業まで、サクソフォンのプレイヤーとしてステージに立つこともありました。そのときに見たステージを裏で支える人たちに惹かれて、今では会場の施設管理者としてイベントの裏側を支える毎日です。イベントやエンターテイメントなどで得た体験が、人生の中で必要かどうかはその人次第ですが、一人でも多くの方に共感してもらえたら、それはうれしいです。
私は、演劇を通して出会いが各段に広がりました。同世代だけでなく、ベテランの方とお話するような経験を得られたんです。シアターワークショップで企画した即興演劇のワークショップでも、ふつうなら交わらないような20代から70代、80代の方々が、即興劇で同じ世界を演じたりしました。
そんな人と人の新たな関係性を構築できる場を事業として行っていきたいと思っています。
お話を聞いていて、今の仕事をしていなかったら何をしているだろうと考えてみましたけど、思いつかない…。私も学生時代はミュージカルで演じたり、裏方をやっていました。そのときに舞台に立つ人たちを劇場づくりという形で支える仕事がしたいと思って。
文化芸術で心豊かな社会を形成するという命題は常に根底にあって、それをどう実現していくかがミッションだと思います。
最近は敢えて仕事のことを考えない時間も作ってみたりしていますが、私は「趣味が舞台照明です」というくらい、普段から照明やアーティストのことを考えて生きてきました(笑)。海外の方ともたくさん仕事をしましたし、人と出会える刺激的な日々が楽しいです。コロナ禍を経て、やはり劇場やイベントスペースのような場で直接人と出会うことで得られる価値があり、その場所を大切にしていかなければならないというのも痛感しましたね。
日常生活のほうが作り込まれた劇よりはるかに劇的ですよね。それでも、なぜ「劇場」に来るかというと、やはり非日常を味わいたいからだと思います。自分の人生では起こりえないことを演劇やコンテンツを通して体験し、人は心を動かされます。疑似体験的なものでも、実際に目の前で接したり、なんらかの手触りや肌触りが感じられることでよりリアルに近づくわけで、その要素はとても重要だと思います。
劇場で体験できることのおもしろさを多くの方に伝えたい。人と人が出会って何かが得られる場所=劇場が、誰かにとってのセーフティーネットになる場合もあると、僕は考えています。

受け継ぐということ
– ここにいる皆さんは、仕事だけでなく年齢もバラバラです。
仕事にまつわることで、時代により「変わっていくもの」と「変わらないもの」はありますか。
照明でいうと、近年はLED電球など新しい技術が舞台にも取り入れられています。変えてはいけないものを守るのは大事ですが、より良くなるのならベテランがブレーキをかけてはいけません。私は若手を後押しできるような存在でいたいと思っています。
ただ、昔に比べて技術は進んでいますが、たとえばフェードアウト(少しずつ照明の光量料を下げていく技術)のときに、これまでの電球との違いが顕著に出ます。これまでの電球だと「ふわっ」と徐々に消えていたところが、LEDだと「パッ」と急に消えてしまい、余韻がちがうんですよね。そこは課題に感じています。
わかります。LEDはとにかく明るく光りが強いので、メディア発表会の場などで使うことは多いですが、深みを出したい演劇では追いついていません。色温度の調整可能なLEDも出てきているので、これから進化していくのではないでしょうか。

年々コストも上がっているので、いつまでも白熱電球にこだわっていられない(笑)
そういうことが肌でわかるのは経験があるからですよね。それに、シアターワークショップのどの分野もひとりでできる仕事ではなくて、チームで動いている。人との接し方やものづくりのマインドは時代が変わっても変わらない。その原点を学ぶには、やはり経験豊かなベテランから教わるしかありません。その点、たくましい先輩方が在籍して、少し年上の目標になる身近な先輩もいる年齢構成は非常に良いと思っています。
40周年を迎え、この先に築くもの
– シアターワークショップは「劇場コンサルティング」「舞台技術」「文化施設運営」「文化事業プロデュース」を手掛ける4つの部門に改編されました。
これだけ幅広い年齢・職業の人たちの中で、どんな想いで仕事をしていますか。
シアターワークショップは音楽制作会社でもなければ、劇団でもありません。つまり、完成品をパッケージで販売する仕事ではないんですね。劇場・ホールに合わせて、すべて手づくりでクリエイティブなものを盛り込んでいかなければなりません。これは難しいぞと感じることでも、喜んで引き受けて、とことん向き合うのが僕たちです。
いつだってオーダーメイドです。文化事業プロデュースは、実際に劇場やホール、広場まで、あらゆるイベントスペースに来てくださるお客様にどんなイベントを提供し、それがその施設や地域にとってどんな化学反応を起こせるかを考える部門です。中学・高校生が多く訪れる場にしたいというイメージがあれば、その世代に向けたイベントの企画をしたり、自由に出入りできる交流スペースを盛り込んだり。劇場や文化施設づくりの最後のアプトプットのような部分なので、毎回熟考しながら仕事をしています。

劇場プロデュース部門は、シアターワークショップの原点である劇場コンサルティング事業を手掛ける部門です。文化事業プロデュースとは逆で、調査・基本構想・計画・設計者選定など、プロジェクトの始まりのところから携わります。そこに他部門の方々の声をきちんと盛り込んでいくことが非常に重要だと思っています。先ほどのLED照明の話もそうですが、施設が実際に使われるようになってから、その現場で感じていることや起きている課題を直ぐそばで聞けて、次の劇場づくりに活かせるのが強みですね。
世の中には、施設を建てたものの使い勝手が悪いとか、結局設備が使わずじまいになってしまっているといった事例が少なくありません。それでも、その設備のことを詳しく知っているスタッフが使用する方に丁寧に寄り添うことで、今度の企画で使ってみよう、使ってみたら便利だったというふうにできるかもしれない。その点、当社は経験豊富な人材が4部門に在籍していて、お互いに交流することで、どうしてその設備があるのかを理解して使い方まで知ることができますし、現場の使い心地をフィードバックすることもできます。基本構想から建てた後の運営まで、トータル・プロデュースができる構造がありますね。
シアターワークショップに入社して、劇場やイベントスペースをつくる難しさを目の当たりにしました。今までは「搬入口が使いにくい!」とか、仕事をしながら文句を言ってることが多かったですが(笑) それが、今では「使い勝手のいい搬入口にするには、設計者にどう伝えればわかりやすいだろう?」と考えるまでになりました。

演者と観客がいればどこでも劇場になり得る中で、もっと視野を広くもち、より多くの人たちに観てもらうために、より良い劇場、イベントスペースとは何かを常に考え、施設そのものから照明などの舞台技術を含むハードの部分、運営面、そこで起こる出来事の企画まで、トータルでプロデュースするのがシアターワークショップの役割だし、これからもっと実現していかなければなりません。
これからもシアターワークショップにしかできないアイデアをともに生み出し、発信し、実現できたらうれしいですね。
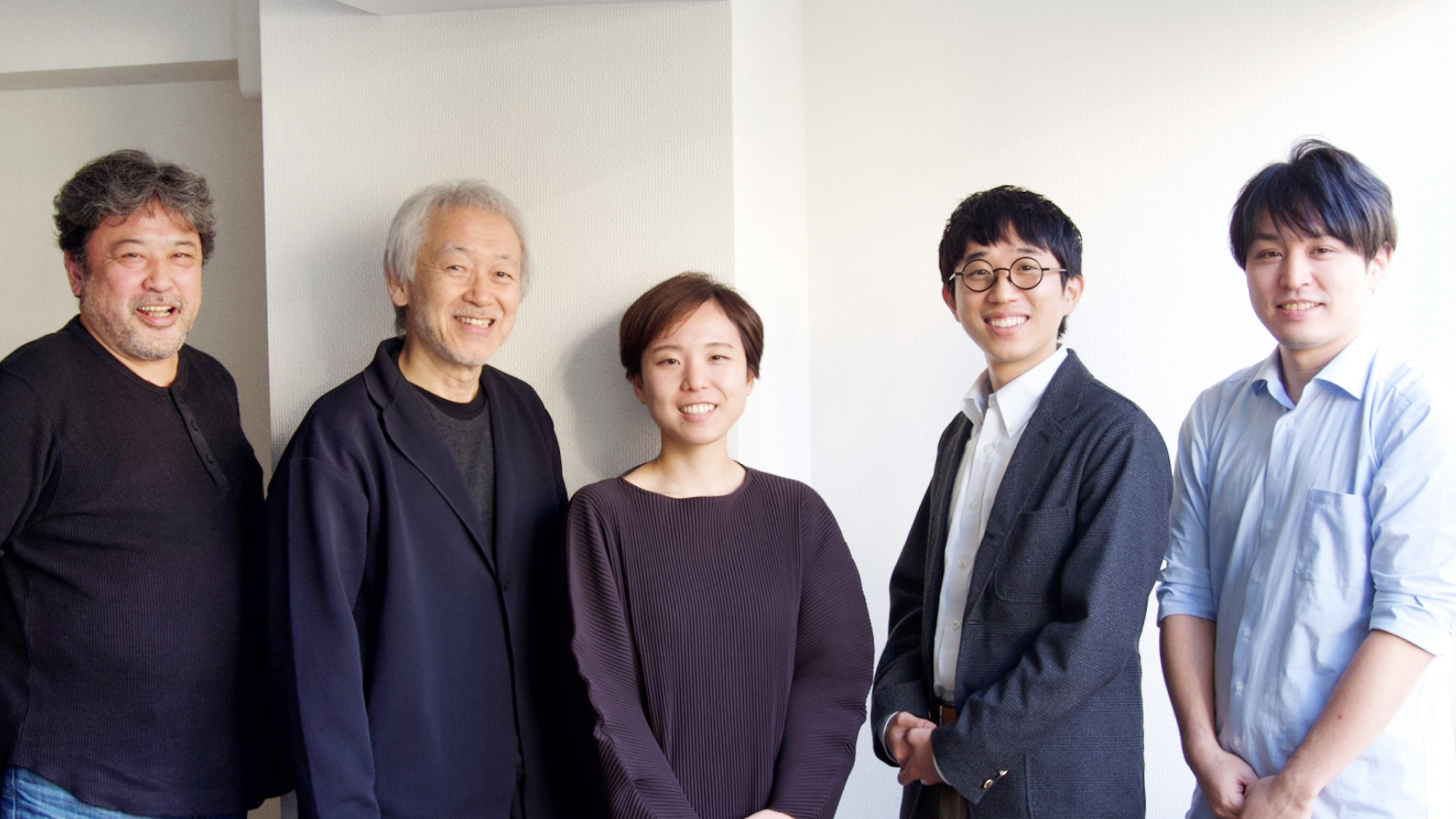
写真左から
テクニカルプロデュース部門 照明チーフ 遠藤 清敏
とくにコンサートの照明技術に長らく携わり、2021年に入社。シアターワークショップ企画の文化事業も含め、全国のイベントに技術参加するほか、劇場コンサルティング時の機材提案や、国内外問わず劇場スタッフに機材の使用方法のレクチャーも行っている。
代表取締役 伊東 正示
早稲田大学・同大学院で劇場・ホールについて研究し、在籍中より文化庁(仮称)第二国立劇場設立準備室の非常勤調査員として活動。1983年にシアターワークショップを設立し、日本で初めて劇場コンサルタントを職能として確立した。 >詳細
劇場プロデュース部門 チーフ 古川 茉弥
学生時代はミュージカル部に所属し、舞台をつくり、演じることを経験。劇場に携わる仕事を希望し、大学・大学院で建築計画を学び、2016年に入社。現在は全国の劇場コンサルティング案件の施設面を担当している。
事業プロデュース部門 長谷川 皓大
大学で広くアートマネジメント分野を学び、自身も即興演劇などを今も作り続けている。文化振興財団の事業担当を経て、2021年入社。全国での文化事業の企画・実施のほか、劇場コンサルティングの運営面などソフト部分も部門を横断して担当。
運営プロデュース部門 マネージャー 中村 諒
学生時代にサクソフォンを専攻し、プレイヤーとしても活動。映像のアシスタントディレクターを経験した後、2015年入社。施設運営の現場でさまざまなイベントを担当し、現在は渋谷エリアの複数施設で運営管理、営業施策の実施などを担う。

